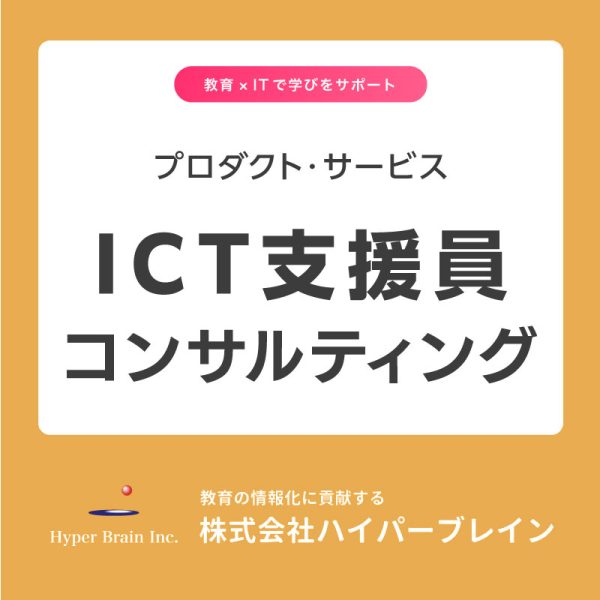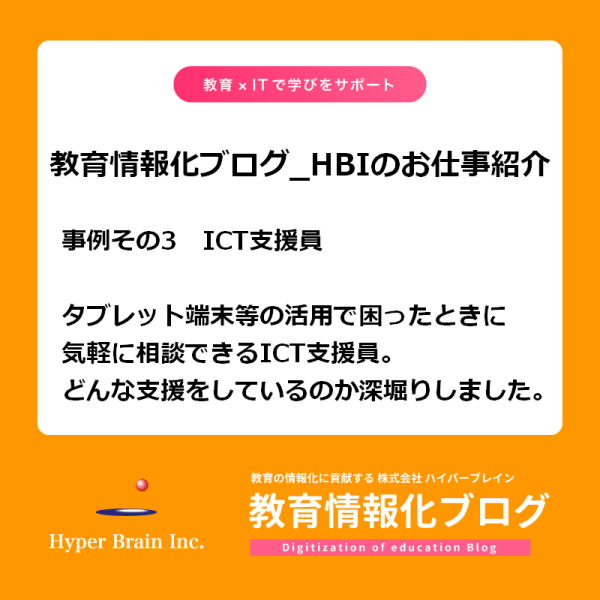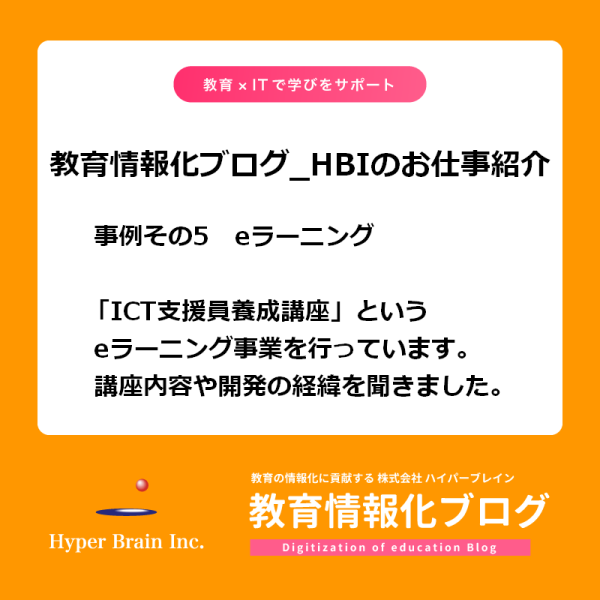ICT支援員とは
直接学校に出向いて、先生方のご支援を実施する、教育ICTの知識を持った専門家です。
一人一台端末が実現したことにより、授業や校務で日常的にICT機器を使用されてきていますが、操作の習得や授業の見直し、機器の準備などを先生方がすべて行うとなると、かなりの負担となります。ICT支援員は、先生方が「先生にしかできない仕事」に集中できるよう、ICTの専門知識で先生方をご支援します。
「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画」(平成30年度~令和4年度、令和6年度まで延長)では、ICT支援員を4校に1人配置することが目標とされています。配置数は年々増加しており、令和4年度末時点で約4.6校に1人配置されています。
ICT支援員の業務の種類は、授業⽀援、校務⽀援、環境整備、校内研修の4種と定められています。これらは、学校におけるICT関連業務のうち「指導」に該当しない業務で、事業者に委ねた方が効率的な業務を除いたものとされています(文部科学省:ICT支援員の育成・確保のための調査研究事業より)。実際には、支援する自治体が仕事を定義し(仕様書だったり、募集要項だったり形は様々です)、その契約に基づいて業務を実施しています。
ICT支援員の主な業務と必要スキル
授業支援
ICT機器・ソフトウェアを利用した授業づくりの支援や、授業で使うICT機器の準備・片づけ、授業中の操作支援などを行います。
効果的なICT機器・ソフトウェアの活用事例の知見をもち、先生方に提案するスキルが必要です。また、機器の準備や操作支援をするための基本知識や、ネットワーク障害やトラブル発生時の一次切り分けをする力が求められます。
校務支援
校務支援システムの操作支援や、教職員が使用するグループウェアの操作支援、ホームページの更新支援などを行います。
児童生徒の個人情報をICT支援員が扱うことは原則ありません。学校で使用されている校務システムやグループウェアの操作方法を理解し、先生方が円滑に校務を行えるようご支援する力が求められます。
環境整備
ICT機器やソフトウェアの棚卸やフォルダー管理方法を、学校の方針や指示に基づいて支援したり、ソフトウェアのインストール支援をしたりします。
ICT機器やソフトウェアの基礎知識を基に稼働状況を確認するスキルや、決められた契約・手順に従って作業支援ができる能力が必要です。
校内研修
研修企画に沿って、研修で利用するテキストや資料の作成あるいは作成支援をしたり、ICT機器やソフトウェアの操作や活用方法について校内研修を実施したりします。
誰にでも分かりやすい言葉を使ってテキストやマニュアルを作成したり、研修を実施したりするスキルが必要です。
基盤的なスキル
その他、いかなる業務を行う場合でもICT支援員が前提としてもっていなければならない共有的なスキルがあります。この基盤的なスキルには、以下のようなものがあります。
- ICT支援員の業務についての理解
- 教育の情報化の理解
- 障害の切り分けスキル
- セキュリティポリシーやコンプライアンスの理解
ハイパーブレインのICT支援員
ハイパーブレインは、実際に学校を訪問するICT支援員のみではなく、チーム一丸で先生方のご支援を行うことを重視しています。
ICT支援員を統括するICT支援員リーダーがいれば、ICT支援員業務に必要な知識や自治体におけるICT運用の基本情報など、訪問前に知っておくべきことを事前研修でレクチャーできます。また、サポートチームがあれば、学校を訪問しているICT支援員からの技術的な質問や自治体独自の運用面での疑問をいつでも受け付けることができ、一定品質のご支援を実現できます。
サポートチームを含めて業務を行うことで、より効果的なICT支援員活用が実施できます。
ハイパーブレインのサポートチームは、教育情報化コーディネータ(ITCE)の1級・2級保持者が高度な専門知識を生かしてICT支援員をサポートします。チームメンバーの情報共有では、即時性のあるチャットによる業務連絡と、経緯・経過を分かりやすく蓄積するICT支援サポートツールd+tasによる業務報告を併用することで最大限に効果を発揮できます。
ICT支援員の1日
学校到着
職員室にて到着のごあいさつの後、本日の予定の直前の打合せ。
1限目の支援の準備
本日は協働学習ツールを使うため、転出入などに伴うアカウントがきちんと処理されているか確認。
1限目
操作に戸惑う子どもについて、担任の先生の指示で少し待ってから声をかける。
休み時間
先生にフィードバック。2限目の支援の準備。
2限目
協働学習ツールの新しい使い方の説明をし、先生の授業の支援に入る。
長い休み時間と3限
先生にフィードバック。報告書入力。調子の悪いタブレットの確認作業。
復調したものはそのクラスにお返しし、修理が必要なもの、保守をするものに分けてそれぞれ関係各所に連絡。
休み時間
特別支援教室でネットワークが不調との連絡が入り駆け付ける。
対象業者に連絡し、アクセスポイントの再起動を指示されたので再起動。とりあえず復調。
4限目
ネットワーク不調の対応をしていたため遅れて入室。担任の先生の指示で操作に困っている子供たちのフォロー。
給食、休憩
掃除の時間
子どもたちは掃除中。5限目の準備。
体育館でタブレットを使うとのことなので念のためアクセスポイントの電源等確認。報告書入力。
5限目
バスケットボールの試合をタブレットで撮影し、チームで確認。
ボールがあるところに団子状になっていることに気づいた子どもがいて、みんなで空いたスペースに走ろう! と話し合う。
休み時間
報告書入力。本日は5限目までの授業で、それ以降ミニ研修を実施予定のため、研修の準備。
Teams for Educationの開き方からの研修なので、手元のタブレットを電子黒板に接続。報告書入力。
研修
下校指導から帰ってきた先生方が集合したので研修開始。
ミニ研修の意図を校長先生からお話しいただき、15分で全員の先生がTeams for Educationで課題を出せるようになった。
その後質疑応答。
打合せ参加
Teams for Educationをどのように授業に使うかの議論に参加。他校での活用方法をお伝え。
結果を取っておけるので、例えば4月の意識と9月の意識を簡単に比較できるなど他校で有効だと先生が仰っていたことを共有。
報告書入力
本日の研修の成果や有効だと思われる事例を記載。出力して教頭先生にご提出。印鑑をいただく。
訪問を終えて帰宅
次回支援に備えて、依頼内容を整理し、必要な調査を実施。ICT支援員情報共有ツールを確認し、管理者とやり取り。
業務終了
ICT支援員業務について
活用がうまくいくICT支援員業務には、以下のチームが必要です。
- 実際に学校に訪問するICT支援員
- ICT支援員を統括するリーダー(特に情報共有の責任者)
- ICT支援員が質問をできるサポートチーム(特に技術的な質問、自治体独自の運用に関する質問)
ICT支援員だけを雇用するのではなく、上記サポートチームまで含めて業務を実施することで、より効果的なICT支援員活用が実施できます。
ハイパーブレインは、長年このチームでICT支援員業務を実施してまいりました。このノウハウと経験を活かし、最も効果的にICT支援員を活用するご提案をいたします。
ご質問や資料請求などは、お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせはこちら
受付時間 9:00~18:00[土・日・祝日除く]
メールでのお問い合わせはこちら